無事、研修会は乗り切った。
正確には、研修会が終わった後の世界旅行の方がキツかった。
南極に始まり、カナダ、アメリカ、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、ロシア、最後になぜか北海道。
なんでこうなったとボクの方が叫びたい。
なんで寒い季節に、こうも選んで寒い場所を走らせんだ?おかげで、エンジンがガソリンごと凍るかと思ったぜ。
そして、帰宅寸前に、リョウコが必ず、次の場所の予告をするものだから、、、。合わせて、数々のむちゃぶり対応に気を使いまくったテツフミ。もはや。研修会の内容など、消耗して、覚えていなさそうな2人だが・・・いや、邪推は良くない。
「へぇ。そんなこともあったんだねぇ」
後日、助手席で、ニヤニヤして聞いている男性。
今回、テツフミは、今、男性2人を乗せて走っている。
フミカズとユウキ
テツフミが休日通っているボランティアグループで知り合った友達だ。
「なんで、最後が北海道なんだろう?」とフミカズ
「リョウコさんが石狩鍋を食べたいと言ったから。ちなみに、浦河にも寄ってきました」
「なるほど」
ボクが神隠しに遭ってしまう現象には、いくつかの条件があることがわかってきた。
「さすがに、8回も神隠しに遭えば、わかりますよ。私以外の人が乗車していること。そして、その人物が何らかの能力を持っているときです。そして、転移は夕暮れにおきます」
ああ、なるほど。
ちなみに、外はいい夕焼けが広がっている。
確かに、リョウコには、物に力や命を付与する能力があった。今回、乗っている2人にも、それに類する能力がある。
「ってことは? 今回もかなりヤバい?」
「そういうことです」
不気味な笑顔を浮かべるテツフミ。うつろな目をして正面のみを見つめている。
フミカズの顔が凍りついた。
「おーろーせー。誰か助けてー」たじろぐフミカズ。
「日頃、散々、人のことを小説にしている無茶振り返し、、、というか道連れです。
書かれたキャラクターの苦悩も少しは、知ってください」
そう、フミカズの能力は、高速タイピングで小説を執筆する能力。さんざん、友人たちは彼の書く物語の中でカモにされてきた。
「さあ、ユウキくん、どこでも君の行きたいところを述べてください」
テツフミが会話の矛先を、後部座席のユウキに向ける。
なるほど。このために、彼を連れてきたのか。
ユウキは、少し考えて、悪魔の笑顔を浮かべる。
「では・・・僭越ながらいかせてもらいます」
「『ゴールドジム』」
いや、マジで走ったよ。世界各地のゴールドジムに。
せっかくだから、すべてのゴールドジムで、アブドミナルとバーチカルチェストだけ制覇してきた3人。入会料金? まぁ、すべての店舗での支払いをクレジットカードで済ませたので、フミカズはしっかりブラックリストに載ったことだろう。
「・・・なぜ、腹筋と胸筋だけをバキバキに・・・」と、息も絶え絶えのフミカズ。
「そこを傷めると、夜寝る時、苦しいからです」
涼しい顔をして、プロテインをといた水素水で、のどを潤すテツフミ。
ちなみに、こことばかりにすべてのトレーニングマシンを楽しんでいるユウキもいたりする。
「無酸素運動だけでは乳酸がたまるから、筋肉痛が半端ないって、トレーナーさんがいってたなぁ」
「悪魔・・・・」
「何とでも言ってください。だったら、次は天国にでも行きましょうか?」
案外近い、天国まで3.5kmの道のり。
ちなみに、それが今年のテツフミのSNSで「いいね」を飾ったトップ投稿らしい。
東京原宿前のゴールドジムで3人を待ってた時。
ボクは駐車場で、のんびり陽だまりを楽しんでいたところだった。
「まてー。ひったくりー」
なにやら、女性の叫びと、その声の方向から走ってくるのは、旧式のスカイライン。いわゆる、ハコスカだ。なんか、マニアが喜びそう。
追いかけて走ってきた女性の方に聞いてみる。
どうしたんですか?
運転席の窓を閉めたまま、尋ねてみる。まぁ、窓を開けたら、運転席に誰もいないことが発見されてしまうんで。
「あの車に、ハンドバックをひったくられたんです!」
女性がスカイラインを指差す。
うん。わかった。悪いようにはしない。
トレーニングにかまけている3人をさておいて、ボクはアクセル全開で走り出した。
スカイラインも気がついたらしい。一気に加速する。
都心でのバリバリのカーチェイス。
やがて、ボクとスカイラインは、渋谷から首都環状線にもつれこむ。
勝負は五分五分。相手が昔の型の車じゃなかったら、軽自動車に勝ち目はない。
ただし、運転席すらも人がいないボクの身軽さをなめてはいけない。
あっさり、たどりついた横須賀でボクはスカイラインをおいつめた。
古い車だったので、燃費が悪く、あっさりガス欠になってしまったのだ。
こら、ハンドバックを返せ。
逃げ道を塞ぎながら、ボクはクラクションを鳴らす。
「なんだと、こらあ」
スカイラインから、これまたレトロなつっぱり兄ちゃんが降りてきて、ボクに向かってやってくる。
が。
ボクの無人の運転席を見て、兄ちゃんの顔色が変わった。
「へっ?」
うん。悪いこと言わない。大人しく、ハンドバックを返した方がいい。
「どーなってんだ??」
相手の気が抜けた返事をした隙に、助手席のドアを一気に開いて車内に兄ちゃんを巻き込む。
窓を閉め、鍵をチャイルドロックかけて、出られないようにした上で、ボクは再び、首都高速に飛び乗った。
「ひ?ひぃいいい~」
車内で絶叫する兄ちゃん。
カーオーディオにセットされた携帯電話から110番通報はしておいた。現場では、ちょうどひったくりの事情聴取を行なっていたところだ。
ドアを開け、お巡りさんの前でそれを吐き出す。
ハンドバックを後生大事に抱きしめるツッパリ兄ちゃん。
「あ、私のハンドバック!」
女性が驚く。
無事、ハンドバックは女性の手に帰った。
「君が、助けてくれたのかね?・・・え?」
その警察官の返事を待たず、ボクは東京原宿のゴールドジムを目指す。
多分、運転席が無人なのは・・・気づかれたか、気づかれなかったか。
東京原宿のゴールドジム前に戻ってきたのは、その30分後。
ぼーっして、所在なく立ちすくむ3人がトレーニングを済ませて、唖然としてるところだった。どうやら、ボクがいないので、帰れなくなっていたのだ。
3人とも待たせたね。
「あ”~ん」
思わず泣き出す3人。まったく、情けないなぁ。さあ、乗って。でないと、また、置いていくぞ。慌てて、乗り込む彼ら。ボクは一気に長崎に転移した。
教訓。首都高速は気持ちいい。
テツフミが寝ている時に、また一人で走りにくることにしよう。

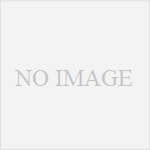
コメント